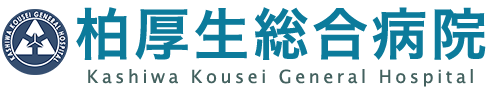消化器科 食道がんについて
●食道とは
のど(咽頭)から胃の間にある管状の臓器で、成人で大体25 – 30 cmの長さです。
頚部食道、胸部食道、腹部食道に分かれています。がんができやすいのは、胸部食道の中部から下部です。
食道の壁は厚さが約4 mmくらいですが、各層があり、内腔側から、粘膜、粘膜下層、筋層、外膜に分かれています。ほとんどの癌は粘膜の表面の上皮から発生します。
●食道がんについて
男女比は6 : 1で男性に多く、年齢では60歳以後に多い病気です。生活習慣とも関係があり、喫煙と飲酒を共に嗜む人では発生率が9倍になります。食道がんは胃がんの8分の1くらいの発生率で、高齢化と共にやや増加してきていますが、その治療成績は向上してきています。
食道がんは粘膜から発生しますが、食道の壁はリンパ管が豊富なため、がんが粘膜下層に及ぶと、リンパ流に沿ってがん細胞が移動して、リンパ節に転移する頻度が増加します。リンパ流には、食道に沿って上方向と下方向のものがあり、手術ではリンパ節も一緒に切除すること(リンパ節郭清)が重要になってきます。
●食道がんの進行度
食道がんの進行度(病期)については、壁の深達度と転移の程度によって、病期0から病期IVBまでに分類され、その病期に応じた治療を選択することが重要です。
食道がんの診断が内視鏡での組織診断で確定すると、その病期を治療前に推定するために、頚部から腹部までのCTや、超音波検査、必要に応じてMRIなどを行います。下の表1は、食道がんの深達度、リンパ節転移や遠隔転移の有無など、病期を分類する際の各因子についての説明です。食道がんの深達度については図2に示しています。進行度分類は、治療方針を決めるときに使う「臨床的進行度分類」と、切除した病変を病理診断し、実際のがんの広がりを評価した「病理学的進行度分類」があります。日本で食道がんに多い組織型である扁平上皮がんの臨床的進行度分類について、表2に示します。
表1 食道がんのT・N・M各因子の分類(食道癌取扱い規約第12版)

日本食道学会編.臨床・病理 食道癌取扱い規約 第12版.2022年金原出版
図2 食道がんの深達度

日本食道学会編.臨床・病理 食道癌取扱い規約 第12版.2022年金原出版
表2 食道がん(扁平上皮がん)の臨床的進行度(ステージ)分類
ああああああああ(食道癌取扱い規約第12版)

●食道癌治療の選択
治療は、がんの進行度(病期)に応じた標準的な治療を基本として、ご本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。図3〜図6は、食道がんの標準的な治療を示したものです。
(1)0期の治療
図3 食道がんの治療の選択(0期)

日本食道学会編.食道癌診療ガイドライン 2022年版.2022年,金原出版
粘膜にとどまるがんでは、食道を温存できる内視鏡的切除が標準治療として推奨されています。
内視鏡的に切除したがんを含む組織は、病理検査で詳細に調べます。がん細胞が粘膜下層に浸潤している、リンパ管や静脈に侵入しているなど、がんが残っている可能性やリンパ節転移の可能性が高いと判断された場合は、内視鏡的切除後に手術や化学放射線療法などの追加治療をおすすめします。粘膜にとどまるがんのうち、がんが食道の全周近くに及んでいた場合、かつ長さが5cmを超える場合などには、手術または化学放射線療法または放射線治療を行います。なお、内視鏡的切除を行った場合で、がんが食道の3/4周以上に及んでいるときは、狭窄予防のための治療が行われます。
日本食道学会編.食道癌診療ガイドライン 2022年版.2022年,金原出版
Ⅰ期では、手術または化学放射線療法が標準治療として推奨されており、体の状態によっていずれかを行います。
(3)Ⅱ期・Ⅲ期の治療
図5 食道がんの治療の選択(Ⅱ期・Ⅲ期)

日本食道学会編.食道癌診療ガイドライン 2022年版.2022年金原出版
Ⅱ期・Ⅲ期の標準治療は、治療前に体の状態を調べて、手術が可能な体の状態である場合には手術が第一選択です。その中で、まず、抗がん剤を用いた化学療法を行ってから手術をする方法が標準治療とされています。化学療法を行わずに手術を行った場合は、その後の病理検査でリンパ節転移が認められた際には、術後化学療法を行うことがあります。
手術も化学放射線療法も不可能な体の状態であると判断された場合は、放射線単独療法や化学療法などを行います。
(4)Ⅳ期の治療
図6 食道がんの治療の選択(ⅣA期・ⅣB期)

日本食道学会編.食道癌診療ガイドライン 2022年版.2022年金原出版
ⅣA期では、化学放射線療法が標準治療として推奨されています。
ⅣB期では、化学療法が標準治療として推奨されており、免疫チェックポイント阻害薬と抗がん剤を組み合わせた治療を行います。体の状態を確認して、治療が可能かどうかを検討します。
がんによる痛みや狭窄などの症状がある場合は、症状を緩和する治療を行います。
●食道がんの内視鏡的切除
内視鏡的切除は、内視鏡を用いて食道の内側からがんを切除する方法です。切除方法として、高周波ナイフで粘膜下層から病変をはぎ取るように切除する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)(図7)を行っています。内視鏡的切除の対象は、リンパ節転移のない0期の早期食道がんのうち、食道の全周に及んでいない場合や、全周に及んでいる場合は5cm以下の場合です。なお、がんが食道の3/4周以上に及んでいる場合には、内視鏡的切除後にステロイドを局所注射して、狭窄を予防します。内視鏡的切除の合併症として、出血、穿孔、狭窄などがありますが、その多くは内視鏡を使って対処することができます。切除したがんを含む組織は、病理検査で詳細に調べます。がん細胞が粘膜下層に広がっている、リンパ管や静脈に侵入しているなど、がんが残っている可能性やリンパ節転移の可能性が高いと判断された場合には、内視鏡的切除後に手術や化学放射線療法を行うことがあります。
●食道がん手術
手術は、がんを含めた食道と胃の一部を切除し、同時にリンパ節を含む周囲の組織も切除します(リンパ節郭清)。食道切除とともに、胃や腸を使って食物の新しい通路を造る手術(再建手術)を行います。がんが、食道のどの部位にあるかによって手術の方法が異なります。
病期Iと病期IIの場合、手術治療の効果は良好です。
病期IIIの場合には、放射線療法や抗がん剤と組み合わせて行うことが多くなります。術前にT4(他臓器浸潤)が予想された場合には、原則的に手術は行いません。
手術の方法は病巣の位置により、異なります。
1.頚部食道がん
頚部食道を切除して、咽頭と胸部食道の間に空腸の一部を移植します(遊離空腸)。血管吻合を行い、空腸への血流を確保します。頚部リンパ節郭清も行います。ただし、頚部には重要な血管や神経も多く、発声や嚥下などの機能を温存する必要があるため、最近では、手術治療よりも化学放射線治療を行うことが多くなってきています。
2.胸部上部食道がん
まず右開胸を行い、縦隔(胸部の中央の部分)のリンパ節郭清を行います。胸部上部において、食道は気管に近く、手術では注意を要します。胸部食道を全摘して、通常の場合においては、再建臓器として胃を用います。開腹を行い、腹部のリンパ節郭清を必要に応じて行います。胃の一部を切除して管状にしたもの(胃管)を血管と一緒に、横隔膜の隙間を通して、もとの食道があったところにもってくるようにします。頚部のリンパ節郭清を行ってから、頚部に胃管を挙上して、頚部食道と胃管をつなげます(頚部食道胃管吻合)。胃がない方では、再建臓器として、主に小腸、ときに大腸を用います。
3.胸部中下部食道がん
多くの場合に、まず開腹を行い、腹部のリンパ節郭清を行いながら、胃の一部を切除して管状にしたもの(胃管)を作成します。次に右開胸を行い、縦隔のリンパ節郭清を行います。胸部食道をほぼ全摘して、横隔膜の隙間から胃管を胸腔内に引き上げてきて、頚部食道に近い胸部上部食道と胃管をつなぎます(高位胸腔内食道胃管吻合)。上縦隔のリンパ節に転移が疑われた場合には、胸部食道を全摘して、頚部リンパ節郭清を追加することもあります。胃がない方では、再建臓器として、主に小腸、ときに大腸を用います。
4.腹部食道がん
開腹を行い、胃の周囲のリンパ節を確認します。胃に近いリンパ節に多くの場合に転移があり、根治性の観点から胃全摘をした方がいいと判断されることもよくあります。その場合、横隔膜を腹部から切開して、下縦隔のリンパ節郭清を行い、胃全摘して腹部リンパ節郭清を行ってから、空腸(上部小腸)と胸部下部食道をつなぎます(胸部下部食道空腸吻合)。胃の中下部を残せる場合には、残胃と胸部下部食道をつなぎます(胸部下部食道残胃吻合)。
手術の合併症と当院の手術の特色については、後に別項で述べます。
●放射線療法
放射線療法は食道を温存することを目標にした、局所治療です。放射線を身体の外から照射する方法(外照射)を主に行っています。脊髄麻痺を回避するため、週5日6週くらいが最大限となります。根治的な目的の場合では、転移の疑われる所属リンパ節も含めて照射野を設定するため、広い範囲に照射することになります。
副作用として、白血球数や血小板数の減少(骨髄抑制)や皮膚炎、放射線肺臓炎(肺繊維化)、食道炎などがあります。また、頚部に照射した場合、咽頭の違和感や疼痛がおこることもあります。腹部に照射した場合には、腹痛、嘔気、食欲低下、下痢などがおこることもあります。治療が終了して時間がたってから心臓や肺に障害が起こることもあります(晩期障害)。副作用の出現には、個人差が大きく、もしひどい場合には治療を中断することもあります。多くの場合、時期が来れば自然に回復します。
放射線療法を行う際に、同時に抗がん剤治療を追加した方が、放射線療法単独の場合に比べて、効果があることが、最近わかってきました。根治を目的とする場合は、放射線療法と抗がん剤治療を同時に行う方法(化学放射線療法)が勧められます。
がんの拡がりのため、切除不可能と判定され、遠隔転移がない場合に根治的化学放射線療法の適応となることがよくあります。化学放射線療法の効果を判定して、癌が縮小しているがまだ残っている場合に、手術が可能であることもあります。
また、最初に手術を行い、がんが残っている可能性のある場合に、手術後にその部分だけに放射線治療を追加することもあります(再発予防照射)。
●化学療法(抗がん剤による治療)
抗がん剤は、全身投与するため、手術や放射線治療と異なり、全身療法として位置づけられます。しかし、抗がん剤単独での効果はそれほど大きくはありません。可能な限り、放射線治療と組み合わせるようにしています。多くは遠隔転移がある場合や再発した場合に行います。
抗がん剤の副作用には個人差がありますが、嘔気、白血球数や血小板数の減少(骨髄抑制)、食欲不振、下痢、腎障害、色素沈着、口内炎などがあります。嘔気を軽減させる薬剤の投与も予防的に行っています。
●手術の合併症
手術の後に発生する合併症として、肺炎、縫合不全(吻合部のほころび)、肝障害、腎障害、不整脈、心機能低下などがあります。これらの発生率は手術前に臓器障害をもっている患者さんでは高くなります。
食道切除術後の肺炎の合併率は、全国的には20%前後と報告されています。食道胃管吻合の縫合不全の合併率は、全国的には10%前後と報告されています。
自験例(諏訪)では、2002年4月から2022年12月までの集計で、食道切除術後の肺炎は、約10%で、縫合不全は2%以下でした。
●当院の手術の特徴
食道外科手術を専門としてきて、以下のような工夫を行ってきました。
1.食道を切除するときに右開胸を行いますが、筋肉温存、肋骨非切離での小開胸操作に努めています。
後背筋は完全に温存して、前鋸筋も最小限の切離にとどめます。このように大きな筋肉を温存し、さらに開創方法の改良がすすみ、完全に肋骨非切離での開胸操作が可能になっています。このことで、手術後の呼吸機能回復の迅速化と呼吸器合併症の低下が得られています。
2.食道切除後の再建経路として、術後の摂食が良好な、後縦隔経路再建や高位胸腔内吻合による再建を行っています。
従来から広く行われてきた胸壁前経路再建や胸骨後経路再建にはいろいろな問題が指摘されてきました。
胸壁前経路再建では、胸部前面から胃の膨らみが見えるという美容上の不利益と、経路が長いため、吻合部の血行不良による高い縫合不全合併率が問題でした。
胸骨後経路再建では、胸骨と心臓の隙間の狭いスペースに胃があるため、不整脈の出現や摂食不良が問題となっていました。
一方、後縦隔経路再建や高位胸腔内吻合による再建では、食べた物がストレートに胸腔内を下に流れるため、術後の摂食が良好です。縫合不全の合併も少なく、術後成績も良好です。
当院は日本食道学会において、2014年以来、食道外科専門医認定施設として認定されています。
短期および長期の手術成績において、食道外科専門医施設の優位性が示されています。
逆流性食道炎(胃食道逆流症)について
●逆流性食道炎とは
逆流性食道炎とは、胃酸などを含んだ胃内容物の逆流による食道の炎症をいいます。胃酸は非常に強い酸性を示すため、食道に逆流すると食道の粘膜に炎症を起こします。食生活の欧米化、肥満、高齢、ストレス増などが原因となり、最近、日本人に逆流性食道炎が増えています。
●症状
最もよくみられる症状は、胸やけであり、みぞおちの辺りから胸の下の方へかけて、焼けつく、あるいは、熱くなるような不快感が出現します。のどの方まで上がってくる感じや、痛みを伴う場合もあります。その他、口まですっぱいものがあがってくる、食べたあとにムカムカする、胃や胸が痛むといった症状があります。また、慢性的な咳の原因となっていることもあります。
●食道のしくみ
食道には食物をぜん動運動によって胃の中に送り込む機能があります。食道は横隔膜(おうかくまく)を貫く食道裂孔(しょくどうれっこう)を通って胃に通じています。横隔膜は、食道をしっかりと支える働きをしています。また、食道には食べたものが胃から逆流しないように、逆流防止機能が備わっています。
●胃液(胃酸)が逆流しやすくなる原因
A.下部食道括約筋のゆるみ
年齢とともに、食道と胃のつなぎ目でバルブのような働きをしている筋肉である“下部食道括約筋”のしまりが悪くなり、胃酸が逆流しやすくなります。
B.食道裂孔のゆるみ
食道裂孔も食道と胃の境界部を外側から締め付けていますが、食べ過ぎの習慣や年齢とともに緩んでしまい、ここから胃がはみだす“食道裂孔ヘルニア”になることがあります。この場合、胃の一部が横隔膜より口側に脱出しているわけですから、さらに胃液が逆流しやすくなります。
C. 胃の圧力の上昇
肥満や妊娠などでも、腹圧の上昇に伴い、胃にも圧力がかかり、逆流しやすくなります。

●逆流性食道炎の治療方法とは
通常、次の3つのステップで治療が行われます。
A.生活習慣の改善
逆流性食道炎の症状は、日常生活の改善だけでも緩和されることがあります。暴飲暴食、早食い、食後すぐに横になることは、逆流性食道炎にとっては三大悪です。以下に具体的な注意点を述べます。
1.胸やけを起こしやすい食品の摂取を控える。
脂肪分の多い食物、チョコレートなどの甘いもの、柑橘類、コーヒー・紅茶、香辛料、アルコール類、タバコなどは胃酸の分泌を高める、あるいは、胃内での食物の停滞時間が長いため、逆流を起こし易いとされています。
2.食後すぐに横になると胃酸が逆流しやすいので、食後1-2時間は横にならないようにする。
寝るときに胸やけが強い場合は、寝る前の食事は避け、夕食の量は少な目にして、上体を少し高くして寝ると効果的です(寝るときに頭部が10-20cm程度高くなるように、クッションやマットを折り曲げて布団の下に敷く等)。
3.日常生活において腹圧を上げないようにする。
重いものを持たない、前屈みを避ける、ベルトを強く締めないように気をつけます。 腹圧が上がることによって逆流しやすい状態になります。
4.肥満解消に努める。
ゆっくり食べるようにして、食べ過ぎないようにします。過食は胃酸の分泌や胃内の圧を上げるため、特に夕食はあっさりとしたものをほどほどに摂るように留意するようにします。
B.薬物による治療
逆流性食道炎の薬物治療は、症状を和らげる対症療法になります。すなわち、逆流を抑えるのではなく、薬を用いて、逆流する胃液の量を減らしたり、胃酸の酸性度を減らしたりします。薬で症状を和らげるとともに、先に述べた生活上の注意点を守っていくことが大切です。治療薬としては、以下の様な薬物が用いられます。
1.胃酸分泌抑制剤
胃酸の分泌を抑える薬で、プロトンポンプ阻害剤(PPI)を主に用います。おおよその効果は90%程度です。逆流性食道炎はきわめて再発率の高い病気ですので、ほぼ一生その薬を飲み続ける必要があり、これらの薬の内服をやめてしまうと、すぐに症状がぶり返してきます。また、稀ですが、これらの薬の副作用として、肝機能障害や消化管障害(下痢や腹痛など)が報告されています。
2.制酸剤
胃酸を中和する薬で、胃酸分泌抑制剤と併用して使われることがあります。
3.消化管運動機能改善剤
食道の運動をよくして逆流してきた胃酸を押し戻したり、胃の運動をよくして胃からの排出を促す働きを高めますが、効果は限定的です。
C.手術による治療
生活習慣の改善と薬物による治療で効果がみられない場合には、手術による治療が必要になります。 手術では、噴門形成術というものを行うのですが、内容としては、逆流性食道炎の原因である、こわれた逆流防止機構の修復を行います。多くの場合に、食道裂孔ヘルニアを併発しているため、手術では、以下の3つの手順で行います。
(1) 胸の中に入り込んだ胃をお腹の中に戻す。
(2) ゆるんだ食道裂孔を縫い縮める。
(3) 胃を食道に巻きつけることにより、逆流防止機構を修復する。
●逆流性食道炎の手術療法の実際
当院では、逆流性食道炎の手術療法として、腹腔鏡下手術による噴門形成術を行っています。


従来の開腹手術と比較して、腹腔鏡下手術では以下の様な利点があります。
・ 創が小さいので、術後の痛みが少なく、美容的にも優れている。
・入院期間が短く、 社会復帰が早い。
手術により、薬でコントロールできなかった症状が、少量もしくは薬を服用しなくても、コントロールできるようになります。
手術は一時的に金銭的負担がかかりますが、ほぼ一生薬を飲み続けることを考えると長期的には手術をした方が治療費は少なくて済むため、米国では手術が広く行われており、安全性と優れた効果が立証されています。